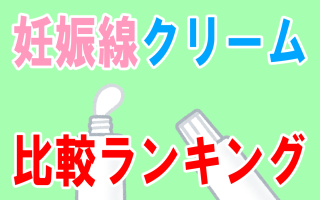子宮頸がん検診とは?クラス(ステージ)と出産への影響
カテゴリ:癌検査
記事の種類:妊婦健診の検査項目
子宮頸がん検診の意味
子宮頸がん検診では子宮頸がんもしくは癌化する前の子宮頸がん(前癌)の有無を診断します。
検査方法
子宮頸がん検診では、一般的にはスクリーニングとして問診、視診、細胞診を実施します。
もし細胞診で異常が発見されれば再検査となり、コルポスコープ診(腟拡大鏡)や組織診などの精密検査を実施して確定診断を行います。
細胞診
子宮頸部の癌の疑いのある部位の細胞を綿棒で擦り取り、染色して顕微鏡で観察します。
1回の細胞診では1~2万の細胞を取得できます。
結果が出るまでには1週間~10日程度かかります。
検査の結果は以下のようにクラスで表されます。
| クラス | 細胞所見 | 推定病変 | |
|---|---|---|---|
| クラスⅠ | 異型細胞は認められない | 正常上皮 | |
| クラスⅡ | 異型細胞が認められるが良性 | 良性異型上皮 炎症性異型上皮など | |
| クラスⅢ | 悪性が疑われるが断定できない | 異形成 | |
| Ⅲ a | 悪性が少し疑われる | 軽度・中等度異形成 5%程度に癌が検出される | |
| Ⅲ b | 悪性がかなり疑われる | 高度異形成 50%程度に癌が検出される | |
| クラスⅣ | 悪性の可能性が極めて高い | 上皮内癌 | |
| クラスⅤ | 悪性 | 浸潤癌(微小浸潤癌を含む) | |
クラスⅢ以上であれば、癌の疑いがあるため確定診断のためにコルポスコープ診や組織診による更なる精密検査を実施します。
コルポスコープ診(腟拡大鏡)
コルポスコープ(腟拡大鏡)を膣内に挿入し、子宮頸部や腟壁を拡大して、炎症や腫瘍の有無を確認します。
具体的には、3%酢酸に十分浸した綿球を子宮腟部に軽く押し当て(酢酸加工)、これを繰り返して腟部表面に白濁する部分か゛出現するかを確認します。
もし白濁すればその形態や程度、消退するまて゛の時間を観察します。
生検組織診
コルポスコープ診で確認した病変を金属製の器具で採取します。
この際、癌の浸潤度も調べるためにある程度の組織を取る必要があり、その際、痛みや出血が生じます。
原因
子宮頸がんの大部分はヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因です。
Noteパピローマウイルス型ではない場合もあります。
治療法
子宮頸がんの進行度は以下のように0期~Ⅳ期で表され、程度により治療方法が異なります。
0期
0期は、異形成~上皮内癌の段階を言い、子宮頸がん全体の約半数を占めます。
0期の治療では子宮頚部円錐切除術(病変のある子宮頸部を円錐状に切除)を実施します。
切除方法としてはコールドナイフもしくはレーザー、高周波電流(LEEP)を用いて、病変のある子宮頸部を切除します。
なお、LEEPによる手術では子宮頸管の奥深くにある病変は切除できないため、病変が子宮頸部に存在する場合に限定されます。
もし妊孕性の温存希望がない場合は、再発防止のために単純子宮全摘出(子宮と腟をつなぐ子宮頸部の靭帯を切って子宮のみを摘出)も考慮されます。
Ⅰ期
Ⅰ期は、癌が子宮頸部のみに認められ、ほかに広がっていない(子宮体部への浸潤は考えない)ものを言います。
ⅠA期
ⅠA期は、組織学的にのみ診断できる浸潤癌で、間質浸潤の深さが5mm以内、縦軸方向の拡がりが7mmを超えない状態を言います。
この内、浸潤の深さが3mm以内の場合をⅠA1期、3mmを超え5mm以内のものをⅠA2期として分類します。
ⅠA期は子宮頸がんのⅠ期以上の内の16%を占めます。
また、ⅠA期の内、ⅠA1期が約90%を占めます。
ⅠA期の治療としては、程度に応じて以下を実施します。
- 子宮頚部円錐切除術(病変のある子宮頸部を円錐状に切除)
- 単純子宮全摘出(子宮と腟をつなぐ子宮頸部の靭帯を切って子宮のみを摘出)
- 準広汎子宮全摘出(子宮、基靭帯の一部と少量の膣を切除※リンパ節郭清(切除)も含む)
- 広汎子宮全摘出(子宮、卵巣、卵管、子宮を支える組織の一部、リンパ節を切除)
脈管侵襲があるものはリンパ節転移のリスクが高いため、リンパ節郭清を含む準広汎子宮全摘出、広汎子宮全摘出が実施されます。
一般的に子宮頚部円錐切除術以外は妊孕能が失われます。
参考但し、妊孕能温存の上での単純子宮全摘出も臨床試験としては実施されています。
もし、妊孕性温存の強い希望がある場合は、脈管侵襲がなく、切除断端が陰性で、頸管内掻爬組織診が陰性の場合に限り、子宮頚部円錐切除術のみを実施します。
なお、卵巣への転移がなければ、広汎子宮全摘出でも根治性を損なわずに卵巣を温存することは可能とされています。
ⅠB期
ⅠB期は、臨床的に明らかな病変が子宮頸部に限局するもの、または臨床的に明らかではないがⅠA期を超えるものを言います。
この内、病変が4cm以内のものをⅠB1期、病変が4cmを超えるものをⅠB2期として分類します。
ⅠB1期、ⅠB2期の扁平上皮癌では、治療法として手術療法(準広汎子宮全摘出、広汎子宮全摘出)もしくは、放射線治療や同時化学放射線療法(CCRT)が選択されます。
同時化学放射線療法は化学療法(抗がん剤による治療)と放射線治療を同時期に開始する治療法です。
化学療法では抗がん剤として主にシスプラチンの使用を中心とした治療計画(レジメン)が実施されます。
Ⅱ期
Ⅱ期は、癌が子宮頸部を越えて広がっているが、骨盤壁または腟壁の下1/3 には達していないものを言います。
この内、癌が腟壁に広がっているが、子宮頸部の周囲の組織には広がっていないものをⅡA期と呼び、この内病変が4cm以内のものをⅡA1期、病変が4cmを超えるものをⅡA2期として分類します。
また、癌が子宮頸部の周囲の組織に広がっているが、骨盤壁まで達していないものはⅡB期として分類します。
ⅡA期、ⅡB期の治療も手術療法もしくは同時化学放射線療法が実施されます。
なお、腫瘍径が4cmを超える場合、卵巣への転移の可能性が高くなるため卵巣の温存が難しくなります。
また、腺癌の場合は、このⅡ期までは、原則として手術療法が推奨されています。
Ⅲ期
Ⅲ期は、癌が骨盤壁まで達するもので、癌と骨盤壁との間に癌でない部分をもたない、または腟壁の浸潤が下方部分の1/3に達するものを言います。
この内、癌の腟壁への広がりは下方部分の1/3に達するが、子宮頸部の周囲の組織への広がりは骨盤壁にまでは達していないものをⅢA期、癌の子宮頸部の周囲の組織への広がりが骨盤壁にまで達しているもの、または腎臓と膀胱をつなぐ尿管が癌でつぶされ、水腎症や腎臓が無機能となったものをⅢB期として分類します。
Ⅲ期の治療では、主に同時化学放射線療法が実施されます。
Ⅲ期以降では手術療法は推奨されていません。
Ⅳ期
Ⅳ期は、癌が小骨盤腔を越えて広がるか、膀胱・直腸の粘膜にも広がっているものを言います。
この内、膀胱や直腸の粘膜へ癌が広がっているものをⅣA期、小骨盤腔を越えて、癌の転移があるものをⅣB期として分類します。
ⅣA期の治療はⅢ期同様に同時化学放射線療法が実施されます。
ⅣB期になると、全身状態が良好で、かつ臓器機能が保たれていれば全身化学療法が実施されます。
全身化学療法は、抗がん剤やホルモン剤等の薬剤を、静脈内注射や内服等の方法で投与する薬剤中心の療法です。
もし肺やリンパ節への転移(遠隔転移巣)がある場合は、転移先の癌が切除可能な場合は切除手術、放射線治療、同時化学放射線療法が検討されます。
合併症の症状が強い場合は原因病巣に対する緩和的放射線治療も併せて実施されます。
陽性の場合の妊娠への影響
母体
早期治療を実施すれば母体生存率は高くなりますが、発見が遅れたり、妊娠継続を希望して治療が遅れれば転移したりなど、予後は悪くなります。
子宮全摘出では卵巣温存が可能な場合もありますが、妊孕性が失われる可能性は高くなります。
- 癌の転移(肺やリンパ節)
- 子宮全摘出による妊孕性の喪失
胎児
ⅠA1期までであれば、通常の分娩が可能です。
ⅠA2期の場合、胎児の胎外生存が可能な場合(妊娠22週0日以降)は帝王切開術による分娩となります。
但し、妊娠22週や23週の分娩では、医学上は早産に分類されますが、一般的に予後は良くありません。(新生児死亡や重い後遺症になる可能性が高い)
このため、母体側のリスクを承知で比較的生存率の高い妊娠24週頃まで妊娠を継続させるという選択肢もあります。(母体側のリスクとのトレードオフ)
もし胎児の胎外生存が不可能な場合(妊娠22週0日未満)は胎児を子宮に置いたまま、非妊時と同様の治療を行います。
ⅠB1期以降では、妊娠初期の場合は継続妊娠は困難であるため一般的には広汎性子宮全摘出術が実施されます。(流産になります)
妊娠中期や妊娠後期の場合は胎児の胎外生存が可能な時期まで妊娠を継続させるか、母体救命を優先させるかを判断する事になります。
公開日時:2017年10月29日 01:41:20
最終更新日時:2022年02月28日 22:25:45
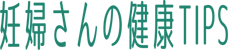
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18bd7ca7.05d282f0.18bd7ca8.e71404bd/?me_id=1296526&item_id=10002668&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Flulu-mavis%2Fcabinet%2Fkodomo13%2Fcs059-dd.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)